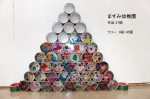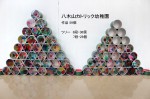11月28日(水)
場所:北上保健医療センターひまわり
講師:武山さん、サポート伊勢さん、
サポート SOAT:藤原、渡邊、佐藤、
参加者:施設利用者・6組 9名
協力:石巻市北上子育て支援センター
9:00~10:00 準備作業、打ち合わせ

10:00~12:00 「クリスマスリース作り」開催
2種類の樹脂粘土を使って「キャンディーケーン」と「マカロン」を作り、作ったパーツや色々な飾りを自由に組み合わせて「クリスマスリース」を作りを行いました。



最初に講師から道具についての丁寧な説明があり、樹脂粘土の種類や扱い方を学びました。参加者は初めて扱う樹脂粘土に興味津々のようでした。
造形体験ではまず講師が作る様子をじっくり見てから、真似て同じように作っていきます。用意した粘土は赤、青、黄、白の4色で、それ以外の色はそれぞれの色粘土を混ぜ合わせて新しく作ります。



「なかなか思い通りの色にならない。」「ちょっと変な形になっちゃった。」と慣れない造形の難しさに戸惑う様子も見られましたが、「柔らかくて気持ちいい。」「ずっとこねていたくなる。」と粘土のさわり心地に癒されながら、参加者同士の会話も弾み、楽しく制作出来ました。
終了時刻ギリギリまで残った粘土で自由な造形を楽しむ方も多く、すっかり粘土の面白さに夢中になったようでした。



参加者の感想
「意外と簡単に出来て、自分でも作れて良かった。」「普段は子供の相手ばかりで集中してやる時間が無いので楽しかった。」等の感想が聞かれました。
振り返り
講師からは「準備は大変だったが楽しかった。」「自分達では揃えられない材料を頂けて助かった。」「託児の体制が無いとお母さん達の参加は難しいが、楽しみにしている方も増えている。今後OGの方も巻き込んで開催していけたら良い。」
講師のしっかりした準備により、スムーズで充実したワークショップとなりました。