11月2日(金)
場所:渡波子育て支援センター
講師3名:百々さん、雁部さん、板橋さん、
サポート2名:金子さん、板橋さん、渡波子育て支援センター職員2名
SOAT:藤原・渡邊・千田教子
協力:石巻市渡波子育て支援センター
布端材協賛:株式会社アクタス、
参加者5組10名
9:00~10:00 準備、打ち合わせ
事前確認では、進行のしかた。布用ボンドの使い方説明確認。布用ボンドの適量を再度確認。

10:00~11:30 「針を使わない花びら巾着作り」開催
花びら巾着作りの全体説明をしてから実際に布用ボンドとアイロンを使って花びら巾着を作りました。






参加者感想:
・飾り付けを付けるのが楽しかった。
・布用ボンドの付け方が難しかったが、楽しく作れた。
・お菓子を入れて散歩に行きます。可愛い巾着が出来て嬉しい。



講師の感想:
・事前に布用ボンドの付け方などを確認しておいたので良かった。
・今回は、全体に説明もできた。分担して教えることが出来て良かった。
・教えるには参加人数が丁度く、ゆっくり教えることが出来た。
12:30~15:00
振り返りミーティング
・地域の世代を超えての交流が出来た。
・手作りは苦手だったが、形になっていく楽しさも体験できた。
・手作りが好きだったので、子育て中に手作りもできその楽しさも伝えることが出来た。
・中々覚えられなくて、教えることが不安だったが準備作業で若いお母さんたちと回数を重ねる度に交流が出来たので楽しく通うことが出来た。このような活動が継続できれば嬉しい。



作成者アーカイブ: SOAT
11月1日宮城県・講師育成講座ステップ②「クレアート」
11月1日(木)
場所:河南子育て支援センター・パプラ
講師:清水さん、
指導サポート SOAT:藤原、渡邊、佐藤、
協力:石巻市河南子育て支援センターサポート5名
参加者13組
9:20~ 会場準備、打ち合わせ



・事前に作成し、季節に合わせた雪だるまや星型などのクリスマスらしい飾りをたくさん用意しました。参加者は基本のパーツセットに加えて自分で選ぶ好みの飾りをフレーム上に自由に配置し、ボンドで接着していきます。
10:50~ 「クレイアート」ワークショップ開催
樹脂粘土パーツを使ったオリジナルのフォトフレーム作りを行いました。
「これは2つ並べようか?」「こっちのほうが可愛いよ。」など親子でコミュニケーションを取りながら仲良く作る姿は微笑ましいものでした。



同じパーツでも並べ方で作品の印象は異なり、自分だけの素敵なフォトフレームを完成させることが出来ました。



・参加者のリクエストに合わせて、SOATスタッフが実際にキャンティーやアイスクリームなどを作って見せました。


 色粘土を混ぜて新しい色が出来ると、子ども達はまるで魔法を見たかのように目を丸くして喜び、粘土が力の加え方で色々な形に変わると、大人も子どもも「すごい!」「なるほど、そうやって作るんだ。」と真剣に見入っていました。
色粘土を混ぜて新しい色が出来ると、子ども達はまるで魔法を見たかのように目を丸くして喜び、粘土が力の加え方で色々な形に変わると、大人も子どもも「すごい!」「なるほど、そうやって作るんだ。」と真剣に見入っていました。
12:00~13:00振り返りミーティング
講師・スタッフからは「忙しい通常業務の中での準備は正直大変だったが、ボランティアの手伝いがあったので出来た。」「お母さん達の笑顔が見られて何より良かった。」等の感想がありました。このような活動が育児で忙しいお母さん達にとって、日々の充実感やコミュニケーションに繋がる大切な時間であることを改めて感じ、来年度以降の具体的な活動のイメージも沸いたようでした。


10月31日宮城県・講師育成講座ステップ②「和紙のランプシェード」
10月31日(水)「和紙のランプシェード」
場所:北上保健医療センターひまわり
講師:伊勢さん、武山さん、
サポート SOAT:藤原、渡邊、佐藤、
参加者:施設利用者・大人9名 子ども2名
協力:石巻市北上子育て支援センター
9:00~ 会場準備、打ち合わせ



・手順や注意点などを確認し、材料のセッティング等を行いました。
・作り方が分かりやすいように大きな図面を用意。
・紙の折り方について指導方法を変えてみる。
10:15~12:00 「和紙のランプシェード」ワークショップ実施
参加者には暗室で点灯したランプシェードを見てもらい、和紙の使い方と作品のイメージづくりをしました。
色和紙をはさみで切る、手でちぎるなどして好きな形にし、土台の和紙に糊で貼り付けてシェード部分のデザインを作っていきます。透かし具合を確認しながら裏表の模様の位置をこだわったり、子どもの手形を利用して紅葉した枝を描いたり、それぞれの世界観で制作を楽しみました。



参加者は子育て支援センター利用のお母さん達で、ほとんどが顔なじみのメンバーでしたが、誘われて今回初めて参加するという方も居ました。制作を行いながらも、普段は距離が離れていたり子どもの世話でゆっくり出来ないお母さん達同士のお話も大変盛り上がり、情報交換やコミュニケションの場にもなっていました。



最後は暗室でライトアップさせて皆で鑑賞会を行い、素敵な出来栄えの作品と記念撮影をして活動は終了です。



振り返り
講師は最初緊張していたようでしたが、事前準備をしっかり行っていた事や、スタッフの託児サポートがあった事でスムーズに活動は進み、お母さん達の「楽しかった!」「次のワークショップも参加したい」という感想と笑顔に、ホッとした様子でした。
10月30日宮城県石巻市/いきがいつくり「積木プロジェクト」2回目
10月30日(火)
開催時間:11:00~12:30
開催場所:こども∞感ぱにー黄金浜ちびっこあそび場
参加:地域住民10名(大人10名)
指導:SOAT 藤原久美子、渡邊廣一、佐藤晴香、
東北生活文化大学教授 森敏美
協力:NPO法人こども∞感ぱにー
木端材協賛:株式会社アクタス、株式会社アカセ木工
<活動の様子>
積木プロジェクトの2回目は参加者が10名と前回より少なく、高齢の男性参加者が1名でした。今回は若い母親が多く、連れてきた子どもの世話と両立させながら活動に参加していただきました。



ワックスを塗って乾かし、磨くという作業と並行して積み木を入れる木箱の四隅に皮を貼って箱の補強と装飾を行う活動がありました。「(ワックスを)どれくらい塗ればいいの。」「磨きはこれくらいでいいかな。」などと初めて会った母親同士が言葉を掛け合い、会話が始まりました。






子育てや地域の情報など、積木プロジェクトが貴重な情報交換の場になりました。また、手先が器用で色々作ることが好きな人からはもの作りの誘いを受けて、活動の場を広げるきっかけを作られた方々もいました。また、皮貼りでは大胆に大きく皮を貼り、個性ある積み木箱を完成させ、作ることの楽しみを味わったママもいました。
活動の最後に、この施設は冬が寒いということで株式会社アクタス様から寄贈されたマット見本を壁に貼る提案をして喜ばれました。






10月25日福島県いわき市/講師育成講座ステップ⓶「布のランプシェード」
10月25日(木)「布製ランプシェード作り」
開催場所:関船団地集会所
講師:仲野さん、サポート3名
SOATサポート:藤原・渡邊・佐藤
協力:NPO法人みんぷく
布端材協賛:株式会社アクタス
住民参加者10名
8:30~9:30会場準備、打ち合わせ
・材料の準備確認。進行確認。

9:30~11:30 「布のランプシェード」ワークショップ実施
布を使ったランプシェード作りの説明をしてから明るい場所と暗い場所での見え方を暗室を使い説明。
土台と布選びでは、あらかじめ用意された中から選ぶことを楽しみながらランプシェード作りが始まった。









参加者は最初「センスが無いから無理。」「アイディアが湧かない。」と自信が無いようでしたが、色々な布を見て手を進めるうちにイメージが膨らみ、どんどん自分らしい色合いや工夫が出てきました。
最後はLEDライトを灯して全員で鑑賞会。
参加者からは「色々な種類の布があって楽しかった。」「イメージ通りにはならなかったけど楽しく出来た。」「初めてで難しい所もあったけれどスタッフさんに丁寧に手伝ってもらったので出来た。」など、むづかしかったけど楽しく制作出来たという声が多く聞かれました。
11:30~12:00 片付け、振り返りミーティング
・普段参加しない方も集まり、より深いコミュニケーションが取れた。「時間通りに無事に終わって良かった。」「地域との繋がりがあったのでどんな準備をすべきか適切に考えられた。」「参加人数が少なめだったので一人一人にゆっくり対応する事が出来た。一緒に作って楽しさを共有できて良かった。」住民と支援員の間で良い関係性が築けていた。

10月24日福島県本宮市/いきがいつくり「積木プロジェクト」2回目
10月24日(水)
開催時間:10:00~14:30
開催場所:福島県本宮市枡形団地集会所
参加:男性5名、女性4名
指導:SOAT 藤原久美子、渡邊廣一、佐藤晴香
協力:本宮市社会福祉協議会
木端材協賛:株式会社アクタス、株式会社アカセ木工
<活動の様子>
ワークショップ内容についてとワックスによる磨き方の説明を簡単に行い、早速作業に入った。これまでのワークショップで4箱やすりがけを終わっていたが、地域の子どもに1箱プレゼントしたいということで、やすりかけの作業から始めた。



男性陣は力強く粗研ぎ用の紙やすりでゴシゴシ磨いていき、細かな仕上げ磨きを女性陣が受け持つという、分業制で行った。本宮の方々は仕事が速く、瞬く間に1箱仕上げてしまった。そこで、ワックスも5箱すべて塗り終えることにした。
10時40分頃に積み木のプレゼント先である保育所の先生と子どもたちが積み木作りの様子を見学に来た。



地区の会長さんが子どもたちに優しく対応し、磨く前の積み木と磨いた後のものを交互に手渡し、その違いを体験させてくれた。ザラザラとツルツルの違いに子どもたちは驚いた様子だった。保育所の先生方も積み木制作の大変さを知っていただくことができ、とても良かった。
13:00~14:00 ワックスを塗ってすでに乾いた積み木にタオルの切れ端を当てて、せっせと磨く作業を行った。



「1カ所40回は磨いてください。」と聞いて、暗算で「1個240回磨くんだわ。あららら。」と言っていたので、少し心配したが、やすりがけ同様、皆さんフルパワーで磨きだした。実際磨いてみると、思ったより大変さがないとわかったのか、おしゃべりが始まった。何気ない日常の会話を楽しみながら積み木磨きを行うことができた。次回の積み木プロジェクトは、プレゼントを待つ子どもたちにきっと喜ばれると、確信して今回のワークショップを終えることができた。
10月18日岩手県大槌町/講師育成講座ステップ②「針を使わないお買い物バッグ作り」
10月18日(木)
場所:大槌町 臼澤寺野ふれあい集会所
講師:佐藤さん、八幡さん、小川さん、地域サポート:4名、
SOATサポート:藤原、渡邊、千田、
協力:NPO法人つどい
布端材協賛:株式会社アクタス
参加者 8名
10:00~13:00 準備作業.打合せ
・参加者が負担にならないように取手付けまで人数分を準備した。
・サイズも自分たちが使い良いサイズをいろいろ考えて決めていた。
・事前打ち合わせでまちの部分の教え方が難しいとのご意見があり教え方のレクチャーを確認して実践をした。


13:00~15:00「針を使わないお買い物バッグ作り」
布用ボンドを使いオリジナルバッグ作りを開催しました。



作り方の全体説明。布用ボンドの使い方、アイロンのかけ方を説明してから作業を始めた。
出来上がった作品を褒め合って喜んでいた。とても良い交流になったようで安心した。



参加者の声
・こんなに簡単にできるとは思わなかった。
・手作りは出来ないと思って参加はやめようと思ったが私でもできたので参加して良かった。
・今日は針使わないで良いのかな?と思いましたが、出来ました。来てよかった。
・ボンドがあるのは知っていたのですが、使い方がわかってよかった。




15:00~15:30 片付け、振り返り講師の感想
・人に教えることが緊張しすぎて出来たかわからないが、みんなが出来上がって安心した。
・自分が納得いかないと作ることも教えることも出来ない。うまく教えることができるか心配だったがみんなが、楽しんでくれて良かった。

10月17日岩手県/いきがいつくり「積木プロジェクト」2回目開催
10月17日(水)
開催時間:13:00~15:30
開催場所:大槌町上町ふれあいセンター
参加:ダンディクラブ(男性4名)、釜石かだっぺし(男性5名、女性1名)
指導:SOAT 藤原久美子、渡邊廣一
サポートSOAT:千田教子、とりまとめ本記録:早坂泉
協力:NPO法人つどい、NPO法人かだっぺし、
木端材協賛:株式会社アクタス・株式会社アカセ木工
<活動の様子>
本日の作業内容とやり方の確認後、早速ワックスがけとつや出しに取りかかった。



黙々とワックスを塗る人、私たちとのおしゃべりを楽しみながら作業を進める人と、いろいろであった。塗るワックスの量はこのくらいでいいのか、どの程度、布でこすって磨けばいいのかなど、熱心に質問する様子はまるで若者そのものだった。
14:00~14:30お茶っこタイム



人の集まるところに顔を出すのが苦手な高齢者が一人いたが、こういうワークショップには引っ張り出すことにしているといっていた。何でも奥さんを亡くしてから外に出なくなったそうだ。「悪いんだけど出てもらってんだ。」とその人に声を掛けると「いや、悪ぐねぇよ。」と返してきた。
4人とも皆70代だが、前向きに生きているようだった。一番明るく振る舞っていたダンディさんから自分のアルバムがないことの悲しさを聞いた。中学校までのアルバムはチリ地震(1960年)の津波で流され、大人になってからのものは3.11で流され、自分の写真は1枚も残っていないと話してくれた。
お互い、どこかで、心の傷に触れないよう言葉を選びながら会話していたのだが、ワークショップを重ねることで信頼関係や絆のようなものが芽生え始めたのではないだろうか。



今回のワークショップでは釜石かだっぺしさんから自分たちの活動内容をもっと広げたいとの希望から皮端材がほしいと言われたり、ダンディクラブの方々から貴重な話を伺うなど、大変充実したものとなった。


10月16日宮城県石巻市・講師育成講座ステップ②「針を使わない花びら巾着」
10月16日(火)
場所:河南子育て支援センター・わいわいクラブ
講師:宮澤さん、大石さん、
SOATサポート:藤原、渡邊、千田
参加者:21名
協力:石巻市河南子育て支援センター
布端材協賛:株式会社アクタス
9:00~10:00事前準備、実施進行打ち合わせ。
事前準備は参加者の作業時間を考えてしっかり行われていた。また、作業を始める前に別部屋で布と飾りのヨーヨーと飾りを選んでから、バック作りと同じく説明・ボンドの作業台とアイロンの作業台を分けて行った。紐通しの印付けとボンドをで貼り付ける作業と飾り付けを参加者に行ってもらうことにした。
10:00~12:30
初めての参加者は、ボンドに不安を感じ多く縫ってしまったためにアイロンで接着する時間が多くかかってしまった。後半はボンド少なめをもっと強調して作業をしたが、全員が仕上がったがゆっくり感想を聞く時間が取れなくて残念だった。



参加者の声
・なかなか自分では手芸などする時間が持てないのでこういう時間があってとても楽しかった。
・今回も可愛い作品を作れると思って参加した。飾りも可愛くできたので嬉しい。
・待っている時間に久しぶりに会ってお話できた人もいて手作りだけでなく良い時間が出来て楽しかった。



講師の声
・手作りのワークショップということで初めてきた方や久しぶりにわいわいサロンに顔を出してくれた方がいて嬉しかった。
・手作りをしたくてもできなくている人たちが多いのかなと感じた。
10月12日宮城県石巻市・講師育成講座ステップ②「和紙のランプシェード」
10月12日(金)
場所:渡波子育て支援センター
講師:金子さん、地域民生委員サポート:4名、職員2名、
SOATサポート:藤原、渡邊、佐藤、
参加:施設利用者 10組
協力:石巻市渡波子育て支援センター・地域民生委員
9:00~10:00事前準備、実施進行打ち合わせ。

10:00~11:10「和紙のランプシェード作り」
始めに、暗室で点灯させたサンプルを参加者に見てもらいイメージをしました。

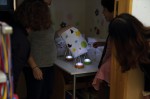
制作は、土台となる白い和紙に、色和紙を好きな形に切ったりちぎったりして糊で貼り付け、自由に飾りを付けていきます。
お子さんは紙を破く、糊を塗るなどの簡単な作業でお母さんと一緒に仲良く参加する姿も見られました。






デザインが出来たら、紙をあらかじめ引かれた線に沿って丁寧に折って立体に組み立てます。最後はライトアップして皆で作品を囲み、鑑賞会を行いました。


参加者の感想
・ちぎって貼るだけで良い感じになって嬉しい。
・子どもと一緒に出来て良かった。
・子どもが一人で遊べるともっと集中して出来たけど、それでも楽しかった。
・裏にも貼ったのが良かった。
・夜に点けるのが楽しみ。
11:10~12:15 振り返りミーティング
講師の感想
・ステップ①受講時から時間が経っていたので忘れている所がありそうで心配だったが、みんな最後は笑顔だったし、親子で作れていたのも良かった。
・教えられるのと教えるのは全然違い、難しい。
・事前準備をしっかりしていたからスムーズにいったし、制作や託児のサポートの手があったから出来た事だと思った。


10月11日宮城県石巻市・講師育成講座ステップ②「針を使わないお買い物バッグ」
10月11日(木)
場所:石巻市河南子育て支援センター・わいわいサロン
講師:大石きよ子さん、・宮澤さん、
パプラボランティアサポート3名
サポートSOAT:藤原・渡邊・千田
協力:石巻市河南子育て支援センター
布端材協賛:株式会社アクタス
参加者 21名
9:00~10:00 準備作業.打合せ
開催場所の準備と事前準備物持ち手付まで事前準備・(脇・マチ・飾り付け)の確認。進行の確認。



10:00~11:30「針を使わないランチバック作り」

講師は、作り方、布用ボンドとアイロンの使い方を説明。オリジナルランチバッグ作りを楽しんでいただきました。






参加者の声
・手作りは苦手なので自分でできたのが嬉しいい。針がなかったので思っていたより簡単にできた。
・子育てで手作りをする時間がないので、自分オリジナルのものができてとても嬉しい。
11:30~12:20振り返り
・説明・ボンドの作業台とアイロンの作業台を分けたことにより小さなお子さんがいる方を3名ずつ順番にワークショップができた。
・説明をしっかり行うことができたことでボンドのつけ方がしっかり理解でき全員がきれいに仕上がっていた。
・飾り付けを選んで参加できたお子さんもいてとても嬉しそうだった。
託児サポートの方から
・どのお母さんたちも完成したバックを持って部屋に戻ってきたときとても嬉しそうな表情をしていました。
手作りは人を元気にさせるようです。ワークショップやって良かったなあととても感じた時間でした。
講師の声
・わいわいサロンに参加してくれた全員がワークショップに参加してくれた。手作りを楽しんでもらえて準備をやって良かったと思いました。
H30年度児童館協働プロジェクト・坪沼自然探検WS/10月20日新田児童館
開催日時:10月20日10:00~15:30
場 所:坪沼八幡神社周辺
参加者数:児童館児童36名 職員5名
講師:齋正弘
サポートSOAT:藤原久美子、渡邊廣一、佐藤晴香、西村優衣子
活動内容詳細:
新田児童館は今年度最後の坪沼自然体験を行った。やる気満々で到着した子どもたちは元気よくバスから降りて「久しぶりー。」「さいじいいるの。」とすぐにSOATスタッフに声をかけてきた。以前参加した時の話や、楽しみな活動の話で盛り上がりながら列をなして神社社務所へ向かった。本殿までの長い石段もそれぞれのペースで登っていった。



社務所で身支度を整えるとさいじいの前に集合した。いつものようにみんなで神様に”よろしく”の挨拶をして探検に出発した。






林の中を進んでいると「かゆくなる草があるから気を付けて。」と声がかかった。慣れた子はむやみに草花に触らずに進んでいったが、初めて参加した子どもの中には全部の草が怖いと言って中々進めない子もいた。どれが触ってはいけないか、どれは大丈夫か進みながら教えてあげると「これは大丈夫。」「あ、これはかゆいやつだ。」「これは怪しいから触らないでおこう。」とひとつひとつ確認しながら進み、林を抜けるころには頼もしい足取りとなっていた。



この日は畑仕事をしている人が多くいたため、遠くから畑を観察した。野菜の葉っぱを見て野菜の種類を当てたり、ハロウィーンで出てくる大きなオレンジ色のカボチャを見つけて大騒ぎしたりした。
畑の脇からヒノキ林へ到着すると、顔くらいある大きな落ち葉を見つけて指で穴をあけお面にして楽しんだ。落ち葉ひとつでも会話が弾み、それぞれの落ち葉のお面で笑ったり、子どもたちは自然の楽しさを発見したのではないだろうか。木の遊具は大人気で、丸太渡りには列が出来るほど集まった。今回は1年生の参加が多かったが、怖がりながらもスタッフのサポートを受け最後まで渡り切り「最後まで行ったよ。」と大きな声で喜ぶ姿が沢山みられた。
昼食後、観察日記の記録担当に選ばれた子どもたちと畑へ出発したが、途中で雨が降り始めたため一旦戻ることとなった。社務所に戻ったころで雨はどしゃぶりになった。しばらく様子を見ることになったが、どしゃぶりの雨に子どもたちは大はしゃぎで、いてもたってもいられず、雨具を着て社務所前に駆け出て雨を楽しむ子どももいた。






雨遊びに飽きた子どもは社務所の中に戻りみんなでお絵描きをして遊んだり、手遊びをして晴れるのを待った。
30分ほど経つと雨脚も弱まり、午後の活動も無事に開始された。野菜の観察日記も無事に実施することが出来た。絵の上手な子が多く、それぞれの野菜の絵を褒めあっていた。


午後もヒノキ林の活動を続けた。女子の中にはどこからか長い木の枝を見つけてきてそれを地面に立てて四角いスペースをつくり「ここ私たちのお家だよ。」とおままごとをする姿もあった。男の子の中には「この木は剣みたい。」「これは銃みたいでかっこいい。」とそれぞれお気に入りの木の棒を見せてくれた。





活動が終わり「来年も来れたらいいなあ。」と少し寂しそうな顔もあったが、みんなで「またね。」と元気に手を振って笑顔で帰っていった。
突然の雨も全身で楽しみ、自然のものを何かに見立てて遊んだり、草木を使って新しいものをつくったりと、子どもたちの創造力と豊かな感受性が大いに発揮された一日だった。