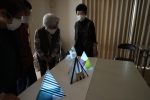令和2年11月19日
時間:13:30~16:00 開催。
開催場所:福島県双葉郡富岡町社会福祉法人富岡町社会福祉協議会福祉センター 小ホール
対象者:地域住民11名
講師・指導:千田教子(パッチワーク・布小物作家)SOAT藤原、高橋、佐藤、
協力:富岡町社会福祉協議会
布素材協賛…株式会社アクタス
サロン活動支援 アートワークショップ「ものづくりワークショップお手伝いボランティア活動」第4回目
13:30~14:00 開催
このプロジェクトについて
住民のみなさんに「お手伝いボランティア」として、ゆうゆう倶楽部のアートワークショップの事前準備をお手伝いしていただいています。今回は11月20日に開催するゆうゆう倶楽部のものづくりで使用する材料などの事前準備と会場設営を、住民の皆さんにボランティアとしてお手伝いをしていただきました。



「お手伝いボランティア」のユニフォームとして、参加住民のみなさんにお手伝いをしていただき、おそろいのエプロンを制作しました。これからもボランティア活動を継続していく「モチベーション」のひとつになった様子で、みなさんにとても喜んでいただけました。これからもよろしくお願いします!


生きがいつくり 「gift by gift 卒業式応援プロジェクト」 2 回目
14:00~16:00
このプロジェクトについて
今年度、SOATは富岡町にお住いのみなさんに「お手伝いボランティア」として、町内での活動をサポートしていただいています。そのお手伝いボランティアでの交流を通して、「もっと町や子供たちのためになにか出来ないか?」とのお話も聞かれるようになりました。そこで、富岡町第一・第二小学校、中学校、三春校の子ども達を応援する活動はどうか?と案がありました。富岡町教育員会、富岡町社会福祉協議会の協力を得ながら、現在を進めています。
今回の活動
第一回目にみんなでつくり始めた花びらを組み立てて、コサージュに仕立てる作業を行いました。参加者のみなさんは自宅にも材料を持ち帰り、コツコツと花びらを作ってきてくださいました。そのおかげですぐに組み立てに入ることが出来ました。



皆さん出来上がりをとても楽しみにしていたので、すべて完成したときにはとても嬉しそうにしていました。
合計で65 個のコサージュが出来上がりました。子ども達へプレゼントする日が待ち遠しいです。





次回にむけて
コサージュの次には押絵とつまみ細工の共同制作に進みます。横180 ㎝、縦90㎝の超大作です。デザインは昨年度、モザイクアート制作時に子ども達に聞いた「富岡町のすきなところ」で挙がった、富岡の町の「海」「桜」「ろうそく岩」」をイメージしました。






コサージュの時よりもパーツの作成個数が格段に増えます。皆さん「暇だからすぐに出来るよ」などとおっしゃいながらも、「誰かのために出来ること」があることが嬉しそうでした。黙々と作業を作っている姿はとてもやりがいを感じているようでした。