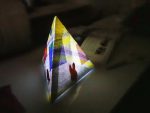8月17日(水)10:00~11:30
場所:成田東小学校砂場
参加者:成田東小学校児童クラブ児童21名(1~5年生) 職員4名
講師:齋正弘 サポート:SOAT3名
活動内容詳細:
前日までの天気予報は曇り、場合によっては小雨ということだったが、晴れた。気温が高いものの湿度が低く、時折吹く風が心地よい活動日となった。齋じいは砂場に集まった子どもたちを前に、熊の話から始めた。


「この辺りは昔、山で熊がいた。熊が落ちるような落とし穴を掘るとしたらどのくらいの大きさの穴が良いと思うか。」齋じいは子どもたちに訪ねることで熊の大きさを具体的に想像させた。子どもたちは動物園で見た熊を思い出しながら穴のサイズを当てずっぽうで答えていた。



齋じいがスコップで砂場に大きな円を描いた。そして穴をみんなで掘るよう話した。3・4年生は円に沿ってスコップで手際よく掘り始めた。



スコップのない子どもは全体の様子を見て円の内側、中央付近を移植ごてで掘り出した。前日までの雨で砂は湿っていたので重いはずだが、協力し合って大きな落とし穴を掘ることができた。子どもたちは穴を掘って出た砂を利用して何カ所か山を作った。



以前、砂場ワークショップに参加したことのある子どもは山の上から水を流すということを覚えていたので、山の頂上から水の流れる方向をどうするか、想像力を働かせながら溝を作った。それぞれの砂山にそれぞれのデザイン。子どもたちが思い思いに溝をデザインした作品群ともいえるものがいくつも砂場にできあがった。



「水を流すぞ。」という齋じいの声で一斉にジョウロを持って水場まで走って行った。ジョウロの水は勢いよく山の頂上から流れた。山はあっという間に水を吸い尽くし、麓まで流れなかった。水の勢いで山に予想外の穴ができると、また山のデザインをやり直したり、壊れないように溝の補強を始める子どももいた。



「水、水!」とあちこちから声がかかると子どもたちは急いで水をくみに水場へ。水場と砂場の往復が始まった。なかにはジョウロを2つ持つ子どもも現れた。どうやったら多くの水を届けることができるか、子どもたちなりの工夫なのだろう。



砂場にわずかだが水が溜まると、裸足になる子どもたちが現れた。「気持ちいい。」「気持ち悪い。」感想はいろいろ。だが裸足をやめる子はいなかった。ジョウロの水をかけてもらったり、流れてくる水に手をつけたりと水の感触遊びを楽しんだ。






活動終了時刻が近付くと、齋じいが砂場を元通りにするよう子どもたちに言った。



子どもたちはスコップの扱いもなれ、キビキビと砂場を元に戻して、活動を終了した。