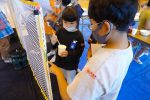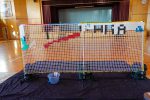2021年11月7日(日)
13:50~14:45 ズーム
会場:エレクトロンホール宮城
新型コロナ対応としてリモートによる発表会となったが、運営側6名のサポートの中で実施した。南は沖縄、北は北海道まで全国に視聴参加者がいたようだ。改めてリモートによる発表の影響力を感じた。


発表前半では東日本震災後、SOATがどう子どもたちに関わり、それがどのようにして児童館とつながっていったか、当時の貴重な写真を交えながら説明した。震災直後は沿岸部の子どもの遊びを支援したが、半年経ってもがれき状態の場所で遊ぶ仙台市内の子どもたちへ支援をシフトする中で仙台市内の5児童館とのつながりができたこと、その流れの中で現在の児童館との出会いがあったことなどが発表された。

後半は「アソビノカタチ」について、SOATが実施しているワークショップをなぜ「アートワークショップ」と呼ぶか、その理由として非認知領域への働きかけがベースとなっているからということを述べた。

東日本大震災時の子どもの様子は全国の児童館職員には貴重な発表だったようだ。アートワークショップという新しいアソビノカタチについても興味や関心を持って頂いた。発表終了後、多くの質問が寄せられ、今回の発表に対する視聴参加者の意識の高さが伺えた。自分たちの児童館でもアートワークショップを依頼できないか、という内容まであり、自分たちの活動が評価されたこともありがたいと思った。
運営サイドの協力を得て無事終了することができました。
ありがとうございました。